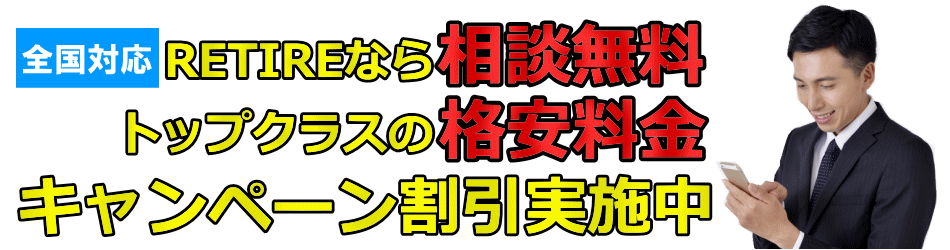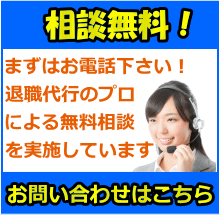Contents
即日退職とは
即日退職とは、会社に退職意思を通知した当日または翌日から会社に出社せずに退職することを意味します。他にも「即時退職・即日退社・即時退社」などと表現されます。即日退職は今すぐにでも会社に行きたくないという人には魅力的な退職方法です。そのため、退職代行業者には「即日退職できます」「明日から会社に行かなくてもOK」といった、気軽に即日退職をすることを勧める宣伝している業者があります。しかし、即日退職を行うにあたっては法律的な制限があり、場合によっては雇用主から損害賠償を請求される可能性があるので慎重に検討する必要があります。
即日退職の法律的な制限
法的には労働者は「退職の自由」が認められており、会社を辞めたいなら辞められる権利があります。ですが、無制限に退職の自由を認めた場合、雇用主側からすれば業務引継ぎがされないまま退職されたことによる損失や担当案件の消滅などによる経済的損失を受ける可能性があるため、退職にあたっては法律上一定の制限が設けられています。
期間の定めの無い雇用契約の場合(一般的な正社員・アルバイト・パート)
期間の定めの無い雇用契約とは、具体的に〇年〇月〇日まで働くといった雇用期間が定められていない雇用契約となります。一般的な正社員はこのような雇用契約となっている場合が多いです。この場合における退職は民法により原則「退職の2週間前」までに退職意思を示す必要があります。
(民法627条1項)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
なお、報酬(=給与)の支払い条件により解約の申し入れ(=退職意思の通知)時期が異なります。
月給制などの場合
ここで言う月給制とは、一般的な会社員の月収条件を示すものではなく、「月あたりいくら払う」といった期間によって報酬を定めた報酬制度を意味します。この場合、遅刻・欠勤による給与控除はありません。このような報酬を定めた場合、翌月以降に解約の申し入れができると定められています。さらに、解約の申し入れは「当月の前半」にしなければならないとされています。
(民法627条)
2.期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
年俸制などの場合
6か月以上の期間定め、期間によって報酬を定めている場合(年俸制など)の場合、3か月前に解約の申し入れを行う必要があります。
(民法627条)
3.六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。
期間の定めのある雇用契約の場合(契約社員など)
契約社員のように、期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)においては、原則として契約期間の途中で退職をすることはできません。なぜなら、労働契約締結時に労働者・雇用主双方が契約期間を定めて合意しているので、契約期間終了前に一方的に退職することは契約義務を果たしていないからです。ただし、やむを得ない事由がある場合は契約期間の途中であっても契約を解除(=退職)することができます。
(民法628条)
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
やむを得ない事由というのは法律的に定義されているものはありません。最終的には司法が判断することとなりますが、「給料が払われない」「パワハラを受けた」「病気・ケガにより職務遂行ができない」といった理由がやむを得ない事由に該当するものと考えられます。
また、有期労働契約の場合、労働契約の初日から1年経過した後は民法628条の規定にかかわらずいつでも退職することができます(例外あり)。
期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成15年法律第104号)附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
つまり、まとめると以下のようになります。
- 原則、有期労働契約に基づく労働者は契約期間中に退職することはできない。
- やむを得ない事由がある場合、契約期間中であっても退職は可能。
- 契約期間の初日から1年経過後はいつでも退職できる(例外あり)。
法律的な制限を破った場合のリスク
労働者には「職業選択の自由=退職の自由」があり、退職自体はできます。ですが、法律の制限を破った場合は雇用主から損害賠償請求を請求される可能性があります。こういった法的のリスクを認識して行動する必要があります。
無断退職との違い

無断退職は会社に一切の退職意思を表明せずに、無断欠勤により退職を図ることをいいます。即日退職とは会社に退職意思を表明している点で異なります。無断退職は会社に対し一切の退職意思表明を行わずに出社しないことになるため、会社側からは退職として認知されず、無断欠勤扱いとなります。そのため、離職票が発行されなかったり懲戒解雇されるリスクがあり、再就職活動に不利となることも考えられます。また、無断退職は会社に損害を与えるケースが多く、会社から損害賠償される可能性が高くなります。
こういったデメリットから無断退職はおすすめできません。無断退職を実行する前に退職代行サービスのご利用をご検討されるようおすすめ致します。
即日退職が可能な場合
では、法律的な制限を破った上で、雇用主から損害賠償請求をされずに即日退職をすることができるのでしょうか。その場合、主に2つのパターンが考えられます。
雇用主の同意
即日退職が可能な1つのパターンとして、「雇用主が同意」を得る事です。雇用契約は労働者・雇用主の2者の契約ですので、双方が合意すれば即日退職は可能ということになります。雇用主の合意がない場合、法律上の制限を守らず即日退職を実施した場合は雇用主から損害賠償請求をされるリスクがあります。
ただし、現実としては雇用主から実際に損害賠償請求される可能性は低いと考えられます。なぜなら、労働基準法などにおいて労働者は雇用主に対し法的に優位な立場であり、訴訟に発展した場合相当な労力と時間が必要とされる場合が多いからです。また、パワハラがあった場合や退職意思を翻させる目的での賠償請求は害悪の告知と判断される可能性があるため、損害賠償請求そのものが不当となる場合があります。そのような場合、雇用主は社会的な信用が失墜する危険性(ブラック企業と認知されるなど)もあるため、会社側が折れて即日退職に同意するというケースが多くあります。また、病気やケガなどで仕事が継続できなくなった場合なども、引き留めしたところで現実的に職務に従事する期待が持てないため、即日退職に同意するケースが多いです。
ただし、労働者が法律的制限を守らず即日退職したことにより受注契約が解約されるなど、会社に損失が発生してしまう場合などは実際に損害賠償請求をされ、裁判において損害賠償請求が認められた事例もあります(ケイズインターナショナル事件(平成4年9月30日東京地裁))。また、全く引き継ぎを行わず即日退職を行ったことにより、退職金が不支給となった判例もあります(大宝タクシー事件(昭和58年4月12日大阪高裁))。こういった事から、即日退職を行うには慎重に検討した上で行動する必要があります。
有給休暇の利用(有給消化)
2つ目のパターンとして有給休暇(年次有給休暇)を利用することで、出社せずに退職における法律的な期間制限をクリアすることも考えられます(=有給消化)。
有給休暇は労働基準法によって定められた「労働者の権利」です。法律的には「理由は問わず」「原則として好きな時に」利用することができます。
1.使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
有給休暇は雇い入れの日から6ヵ月間継続勤務し、全労働日の80%以上を出勤した人に与えられます。雇用形態は問わず、正社員以外にも契約社員やアルバイトやパートであっても与えられます。
有給休暇の目的は、賃金を保障された(=有給)休暇を週休日以外に与えることにより、働く人の「心身の健康を増進させる」ことが目的です。労働者の権利ですので、会社が有給休暇を利用させないことはできません。また、利用理由によって有給休暇利用を拒否することもできませんので、法律的には有給休暇を利用する理由を会社側に伝える必要もありません。また、有給休暇を利用したことにより会社が労働者に対し不利益な取り扱いを行うことは法律で禁止されています。
使用者は、第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
有給休暇の利用時期は働く人の裁量により決定でき、休みたい時に休むことができます。即日退職を目的とする場合でも、退職日前に有給休暇を利用することができます。しかし、ここで注意点が1つあります。それは有給休暇の利用について、使用者(=会社・雇用主)は「時季変更権」があるという点です。
労働基準法 39条
4.使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
時季変更権とは、労働者の有給休暇利用について「事業の正常な運営を妨げる場合」において「他の時季に与えることができる」という、使用者の権利です。時季変更権が認められている背景として、例えば労働者の大半が同時に有給休暇を利用されてしまうと事業運営が正常にできないため、他の時季に利用日を変更させることができる権利を使用者に持たせることで事業の正常運営に影響が少なくするようにさせるものです。
退職の意思を通知した後、以後は退職日まで出勤しないようにするために有給休暇利用を申請した場合、会社側は時季変更権を理由に拒否してくるケースが考えられます。ただし、時季変更権は退職時において主張できるかは疑問があります。それは時季変更権は「他の時季に与えることができる」権利であって、「退職日以後は有給休暇を物理的に与えられない」からです。退職日以後に有給休暇を与えることができないため、「変更する時季」が存在しないため時季変更権を行使することはできないと考えられます。
また、時季変更権ができないのであれば「有給休暇を買い取るから退職日まで出勤しなさい」と言ってくるケースが考えれますが、有給休暇の買取は行政通達により「労働基準法39条違反のためできない」と解されています。
厚生労働省(旧:労働省) 昭30.11.30 基収4718号
年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて年次有給休暇の日数を減じ、又は請求された日数を与えないことは(労働基準法の)第39条違反である。
このため、即日退職のため退職日までの有給休暇利用を買取により拒否してきた場合、会社側の主張を拒絶することが可能です。あくまで有給休暇の趣旨目的は「労働者の心身の健康増進を図る」ことであるため、お金によって買い取る事を認めることは制度趣旨の本質に反するからです。
なお、有給休暇買取については「退職日までに消化できない日数分」を会社に買い取ってもらうことは禁止されていません。他にも「法廷付与日数を超える有給休暇を与えている場合、その超える部分を買い取ること」「有給休暇の消滅時効(2年)にかかり権利消失した有給休暇を買い取ること」も禁止されていません。それらは労働者にとって有利なことであり、法律をもって禁止する必要はないからです。ただし、この場合買い取るかどうかは雇用主の判断となります。
ただし、法律的にはOKであったとしても現実はうまくいかないことがあります。ブラック企業などの遵法精神が乏しい会社などは法律違反であったとしても平気で有給休暇申請を拒否してきますし、「退職なんて無責任なことをする上に有給休暇まで主張するのか!」などと言い、退職を認めようとしないケースも多くあります。
こういったときに退職代行サービスを利用することでストレスを軽減しながら会社に退職意思表示や有給休暇利用を申請することができます。